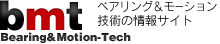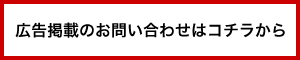東京理科大学・佐々木研究室(主宰:佐々木信也 教授)が主催する「トライボサロン」(https://tribo-science.com/salon)の第31回目が5月10日、東京都葛飾区の同大学 葛飾キャンパスでのオンサイト参加とオンライン参加からなる、ハイブリッド形式によって開催された。

トライボサロンは、トライボロジーに関係する情報・意見交換の場として、毎月1回のペースで開催されている。もともとは佐々木研究室の博士課程学生の勉強会として発足し研究成果の発表や最新の研究動向などに関する意見や情報交換を重ねてきたが、2022年9月からは佐々木研究室に限らず広く参加の戸を開き、関係者のネットワーク作りも目的の一つとして活動している。トライボロジーに関する情報交換、人材交流等を通し、関連技術の向上と発展に資することを目的に、次の活動を円滑に行えるよう運営に努めている。
第31回目となる今回のトライボサロンでは、京都工芸繊維大学・山下直輝氏が、「各種添加剤が形成する境界潤滑膜の可視化とトライボロジー特性評価」と題して、原子間力顕微鏡(AFM)を用いて、①脂肪酸が形成する分子膜と金属石けん膜の評価、②二塩基酸エステル誘導体の分子構造と膜特性の評価、③極性基を多く持つ添加剤のトライボロジー特性評価といった研究事例紹介をまじえて、さまざまなタイプの有機系添加剤が形成する境界潤滑膜の構造を観察し摩擦測定を行った結果について報告した。AFMは摩擦界面における膜構造をナノレベルで可視化しつつ摩擦測定が可能なため、トライボロジー特性の評価ツールとして極めて有効。有機系添加剤が形成する膜形態はさまざまで、単純な分子膜と比較して、脂肪酸金属石けん膜などより柔らかい膜が形成された場合には摩擦係数がさらに低下する傾向がある。また、境界潤滑膜の構造は潤滑油中に含まれる水・酸素、溶解助剤などの微量成分の影響にも左右されるため、精密な環境・条件を制御することによって、より詳細な膜形成メカニズムとトライボロジー特性の理解につながる、と総括した。
トライボサロンに関心のある方は、以下のURLを参照されたい。
https://tribo-science.com/salon