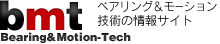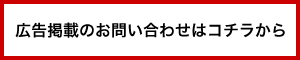三洋貿易は、同社が販売代理店を務める各種のトライボロジー試験機を用いた受託試験のビジネスを開始した。トライボロジー試験機の中期的な販売拡大につなげる狙いで、10月から、メルマガ配信や雑誌広告などを通じて、装置の見込み顧客や試験委託の見込み顧客に対し、同社が受託試験を開始したことを周知し始めている。
三洋貿易では、Falex社、Phoenix Tribology社、STRAMA社に加えて、2017年からはRtec-Instruments製の多機能トライボロジー試験機「MFT-5000」の国内販売を展開してきたが、受託試験はこれまでビジネスとしては行っておらず、装置の購入見込み顧客向けに数サンプルの無償デモを実施する程度だった。しかし、実際には予算やテーマによって装置を購入するほどのボリュームではないが、10サンプル、20サンプルといった時間を要するデモ試験を希望する問い合わせをもらうケースもあり、販売を主とする三洋貿易としては断らざるを得ないケースもあり、装置販売に至らない例も少なくなかった。
これに対し三洋貿易では今回、トライボロジー試験の受託業務を科学機器事業の一つに据え、受託試験という入口を増やして、装置販売の拡大へとつなげる方策を決めた。装置販売の見込み顧客や装置購入の意欲はないがトライボロジー試験を委託したい顧客に対して、受託試験の項目や費用を設定して、顧客の希望するトライボロジー試験を希望する条件で、有償で実施する。三洋貿易が窓口となるが、三洋貿易の所有する試験機、および装置メーカーであるRtec-Instruments社 日本法人や、Rtec-Instruments社製トライボロジー試験機を保有して受託試験を行っている企業、同試験機を用いて研究し試験データを蓄積している東京理科大学 佐々木研究室などのアカデミアといったサポーター・協力者と連携しつつ、受託試験ビジネスを展開していく。
受託試験ビジネスを開始することで三洋貿易は、①見込み顧客が納得感を持ったうえでトライボロジー試験機購入の後押しができる、②装置購入の意欲はないがトライボロジー試験を委託したい顧客から受託サービス料を得ることができる、③上述のサポーター・協力者などのネットワークを活用することで、受託試験の案件ごとに対応者/依頼先の相談が可能、といったメリットが得られる。同社では、受託試験ビジネスを始めることによるデメリットは、関係先も含めて現時点ではないとしている。
受託試験ビジネスを担当する同社ライフサイエンス事業部 科学機器部の田森航也氏は、「受託試験ビジネスは、マーケティングコミュニケーションとアプリケーションの発掘に有効」と話す。
「マーケティングコミュニケーション」の意味するところはトライボロジー試験の受託ビジネス開始を機にトライボロジー関連分野での露出度を増やし、長期間Falex社やPhoenix Tribology社などを取り扱っていたにもかかわらず業界における三洋貿易の認知度が低いという課題を、さまざまなアプリケーションで活躍が期待できるRtec-Instruments社の装置をきっかけに向上させたい、つまり“トライボロジー試験といえば三洋貿易”“摩擦摩耗試験で迷ったら三洋貿易に相談すれば解決できる”というイメージを浸透させることである。
また、「アプリケーションの発掘」の意味するところは、ロードセルやモジュール、環境チャンバーなどの組み合わせによって四球試験やトラクション試験、高温・低温試験や真空試験などさまざまな試験が可能で活用の裾野が広いRtec-Instruments製多機能トライボロジー試験機を使い、受託試験を展開することで、まったく新しい試験アプリケーション、適用可能な産業分野などが見つかる可能性を秘めていることだ。
田森氏は、「取り扱い装置はRtec-Instruments社に限っているわけではないが、日本国内に法人が存在するメーカーであるRtec-Instruments社との連携は深めていきたい。アプリケーションサポート機能や、アカデミアの持つデータ解析・R&Dコンサルティング機能、商社(三洋貿易)のバックアップパーツ・メンテナンスパーツなどを常時保管しつつ保守作業もカバーする機能など、それぞれの持ち味を生かしつつ、受託試験ビジネスを通じて顧客満足度をこれまで以上に高めるとともに、トライボロジー試験機の適用範囲の拡大と中期的な装置販売の伸長につなげていきたい」と語っている。