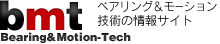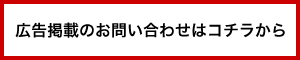トライボコーティング技術研究会、第18回岩木賞贈呈式、第28回シンポジウムを開催
トライボコーティング技術研究会(会長:大森 整 理化学研究所 主任研究員)と理化学研究所 大森素形材工学研究室は2月20日 、埼玉県和光市の理化学研究所 鈴木梅太郎記念ホールで、「第18回岩木賞贈呈式」および「第28回トライボシンポジウム『トライボコーティングの現状と将来』―-DLCによる防汚コーティング,磁気研磨の進化、バイオマスプラスチックの車載応用―(通算第160回研究会)」をハイブリッド形式で開催した。
TOTOが業績名「水垢汚れを抑止する DLCコーティング技術とそれによる浴室鏡の開発」により大賞に輝いた。また、宇都宮大学の鄒 艶華氏が業績名「磁気研磨法による微細複雑形状部品の表面仕上げ技術の開発」により優秀賞を、コニカミノルタジャパン・日本食品化工・新東科学・ハイロックスが業績名「計測試験技術を駆使した新しいバイオマスプラスチック材の車体部品への適用促進技術の構築」により第1回目となる環境賞を共同受賞した
第18回岩木賞受賞者と関係者 水道水に含まれるケイ酸は、鏡の表面で脱水縮合し、鏡の主成分である酸化ケイ素と一体化して水垢となる。水垢が堆積すると、鏡が白い鱗状の汚れで覆われ、視認性低下を引き起す。対象の業績は、水垢の付着・体積による問題に対し、浴室鏡に10nmの極薄膜のダイヤモンドライクカーボン(DLC)をコーティングする技術を開発、この薄さにより透光性を維持したまま水垢の固着を防ぐことが可能となり、簡単な清掃で鏡の映り込みを回復させる機能を実現したもの。DLCコート鏡の生産においては、高密度プラズマ発生器と高電圧直流電源を組み合わせた専用の装置を開発し、最大2mの大判鏡にも高速で成膜できる生産体制を構築した。同社ではこれまで累計200万枚のDLCコート鏡の生産・販売を達成しており、DLCの民生分野への用途拡大に貢献した。その技術の新規性と市場性などが評価されての大賞の受賞となった。
受賞の挨拶に立ったTOTOの園川沙織氏は、「表面改質の研究開発に関わる身として、この分野の栄誉ある賞である岩木賞を受賞し大変光栄。浴室鏡の水垢固着という課題に対しDLCの適用で解決を図る取り組みは前例がなく、1mを超える鏡に真空装置内で高速に量産成膜するなど、数多くの課題があったが、開発チームと共同開発を進めた装置メーカーなどが一丸となって一つ一つ課題を解決し、10年にわたって使い続けられているDLC鏡が完成した。今回の授賞は、研究、開発、生産技術に携わる皆の努力が評価されたもの。今後キーとなった技術のDLCを世の中に広めるとともに、表面がより良い状態となるような技術開発に取り組み、表面改質・トライボロジー分野の発展に寄与していきたい」と述べた。
TOTO・園川氏、TOTO・寺本篤史氏、大森会長
半導体製造装置用の部品など様々な分野で微細複雑形状部品を必要とする製品が増えており、それに伴い微細複雑形状部品をナノレベルかつ高効率に仕上げる精密加工技術が求められている。しかし従来の研磨技術では複雑形状の隅々まで研磨が行き届かず、十分な精密仕上げが困難という課題がある。優秀賞の業績は、新たに変動磁場を利用した磁気研磨法を開発、交番磁場中における磁気研磨スラリーのダイナミックな挙動を利用し、微細複雑形状部品の表面を効率的に仕上げることが可能なほか、磁気研磨スラリーにはミクロンサイズの磁性粒子を用いるため部品表面にダメージを与えることなく、ナノレベルの仕上げを実現できる。半導体部品や3D造形した複雑微細部品の精度向上に寄与する高精度表面仕上げが可能になることが期待されて優秀賞の受賞となった。
受賞の挨拶に立った鄒氏は、「半導体製造装置部品や精密部品ではナノレベルの表面品質が求められる。これに対し変動磁場を利用した磁気研磨法を開発して、高精度の表面仕上げを実現した。来日して27年に及ぶ研究の積み重ね、共同開発者や学生を含めた努力が評価されたものと感じている。引き続き、トライボロジー・精密加工の研究開発を進め、実用化によって社会に寄与していきたい」と述べた。
自動車のCO2削減を目的に軽量化のための部品の樹脂化が進展、特に内装部品におひだりからいてはタルク強化ポリプロピレン(PP)樹脂が適用されているが、使用時の引っかきや擦れに伴う傷が目立ちやすい「白化現象」が問題となっている。これに対し、日本食品化工は、でん粉70%含有バイオマスプラスチック「スタークロス 70PPi」を開発、プラスチック使用量の削減に加えて、鉛筆硬度試験の結果などからタルク強化PPよりも耐傷付き性が高く白化しにくいことが確認されている。しかし鉛筆硬度試験のみでは定量的評価手法とは言い難い。環境省の業績は、PP単独、タルク強化PP、スタークロス 70PPiの3種サンプルに対し、新東科学の摩擦摩耗試験機で摩擦摩耗試験・鉛筆硬度試験を実施し、コニカミノルタの分光測色計および二次元色彩輝度計を用いて上記試験により傷が付いた箇所の見え方を数値化して、比較評価したほか、新東科学の摩擦摩耗試験機でスクラッチ試験を実施しスクラッチ痕の状態などをハイロックスのデジタルマイクロスコープで比較評価し、白化しにくいというスタークロス 70PPiの特性を確認したもの。各社の知見を結集して最適な評価方法の提案を実現したことの新規性や独創性が評価され、環境賞の受賞となったもの。
代表して受賞の挨拶に立ったコニカミノルタの西本昌弘氏は、「自動車業界において循環経済への転換が急務となり再生プラスチックやバイオマスプラスチックの搭載機運が高まる中、当社は日本食品化工のでん粉70%含有バイオマスプラスチック「マーケティングの立場からユーザーでの測色計の適用事例を作成しようと、スタークロス 70PPi」に着目し、これまでの目視や撮影画像による評価という官能評価から、両社による数値評価を目指した。しかし当社の測色計の技術だけでは不十分と感じ、摩擦摩耗試験機の新東科学、デジタルマイクロスコープのハイロックスを加えて4社でプロジェクトを組み、スタークロス 70PPiを定量評価した。ここで得られた評価データやアプローチをプレゼンしたところ、自動車メーカーが賛嘆したとも聞いている。今回の授賞は、各社の今後の仕事の励みになるものと思う」と述べた。
新東科学・北田暢也氏、ハイロックス・上代 永氏、大森会長
贈呈式の後はシンポジウムに移行。岩木賞の記念講演として、大賞に輝いたTOTOの園川氏が、優秀賞に輝いた宇都宮大学の鄒氏が、環境賞に輝いたコニカミノルタジャパンの西本氏ほかの受賞者が、それぞれ講演を行った。